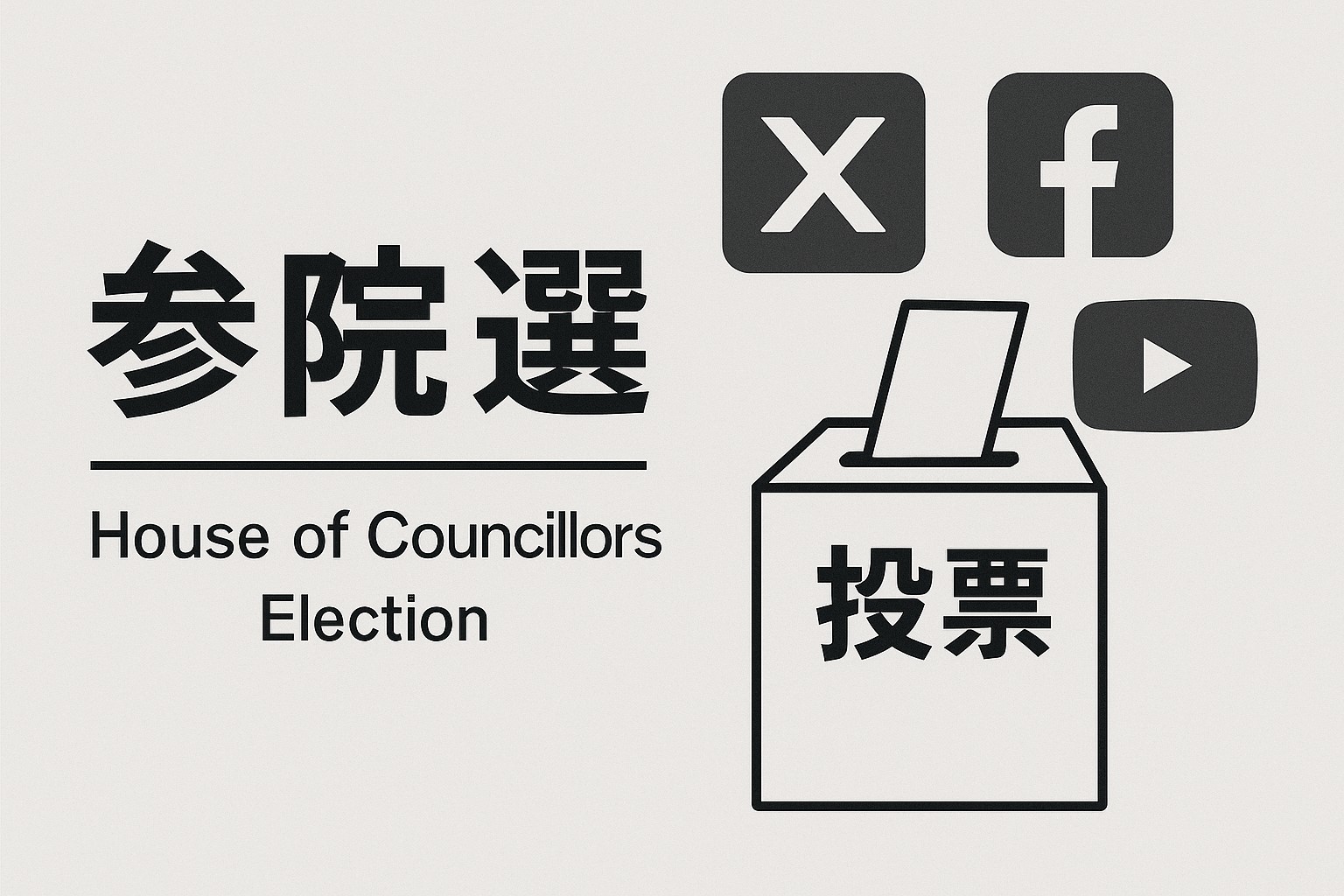参院選と情報の海で迷う
最近、政治関連の話題が身の回りで増えている。
職場でも、「○○党のアレはどう思う?」「今回は投票行く?」なんて声がちらほら聞こえてくる。
おそらく、まもなく参議院選挙があるからだろう。
かくいう自分も、そろそろ投票先を決めなければと考えているが、正直、悩んでいる。
というか、情報が多すぎて何を信じていいのかわからない。
50代にもなると「なんとなくの感覚」では選べないし、どうせ投票するなら少しは自分なりに納得したい。
だけど、その「納得」に至るまでが、なかなか難しい時代になってしまった。
SNSが便利すぎて、逆にしんどい
昔は、政治の情報といえば新聞、テレビ、それに配られる政党のチラシくらいだった。
今ではX(旧Twitter)、Facebook、YouTubeなど、スマホひとつで情報収集できてしまう。
これは便利といえば便利だが、同時に情報過多の地獄でもある。
あちこちから、同じような政治演説の切り抜き、街頭演説の映像、個人の感想、切り取られたワンシーンが流れてくる。
タイムラインには「○○候補は神!」「××党は終わってる!」という極端な主張が並ぶ。
そのどれもが断片的で、「本当なのか?」と疑いたくなる。
特にYouTubeのおすすめ動画に出てくる“解説系”の動画などは、うまく編集されていて一見もっともらしいが、背景やデータの出典が曖昧なまま「この候補は信用できる」「この政党は闇だ」なんて断定する。
そんな動画を見ていると、気づかぬうちに“誰かの思想”を自分の判断だと錯覚してしまいそうで怖い。
技術者的視点で「比較」しようとするも……
自分は製品のハードウェア開発をやってきたエンジニアだ。
つまり仕事では「数値」「仕様」「根拠」に基づいて判断を下すのが当たり前。
だからこそ、候補者を選ぶときにも「比較」「検証」をしたい性分だ。
だが、政治の世界はそう簡単にはいかない。
候補者の公式HPや選挙公報を見ても、耳障りのいい政策が並んでいて、どれも似たり寄ったり。
「経済を立て直す」「子育て支援を強化」「防衛力を見直す」……どれも立派なことだが、中身が具体的でない。
しかも、それらを実際に実行できるのか、法案を通せるのかという点まで考えると、ますます判断が難しくなる。
ネットで調べれば調べるほど、「これって本当か?」「どこまで信用できる?」と疑問が増える一方だ。
情報の波に呑まれる大人たち
そして気がつけば、自分も若者と同じように、アルゴリズムに流されて情報を得ているだけなのかもしれない。
YouTubeで一度「政治系の動画」を再生したら、あっという間に関連動画がずらっと出てきて、気づけば1時間が経っている。
それでも、「調べた気」になってしまうから厄介だ。
何十年と社会人をやってきた人間でも、この情報環境の中では簡単に「印象操作」に引っかかりそうになる。
そう考えると、ネットネイティブ世代の若者たちが情報を精査して投票先を決めるのは、想像以上に難しいのだろう。
SNSの中でしか情報を得ていなければ、「多数派=正しい」と勘違いする構造に巻き込まれてしまう。
それでも投票率が上がらなければ、日本は終わる
ここまで選ぶのが難しい、信じていい情報がわからない、と言っておいてなんだが——
それでも、選挙には行くべきだと思う。
こんなに多くの情報が飛び交い、国の方向性が問われるタイミングなのに、
もし投票率が低いまま終わるようなら、本当にこの国はまずいと思う。
誰が当選しても何も変わらない?
そうかもしれない。だけど選ばなければ、変わる可能性すらゼロだ。
「誰がやっても同じ」と思って白票や棄権をすることが、実は一番“現状維持”を支える行為になっている。
それに文句を言える資格は、本気で投票して、それでも裏切られた人だけだと思う。
エンジニアとして、父親として、50代として
もうすぐ定年が見えてきた。
正直、政治より「退職金の税率」と「年金の受取時期」の方が気になる。
ゲームもテレビも、若い頃ほど夢中になれなくなった。
でも、だからこそ「せめて子どもたちの時代には、もう少しまともな社会を」と思う気持ちは強くなった。
うちの娘はまだ選挙に行ける年齢ではないが、いずれ大人になって社会の一員として悩む日が来るだろう。
そのときに、「うちの父ちゃん、選挙のたびに悩みながらも行ってたな」と思い出してもらえれば、それだけでも十分だ。
おわりに
参院選、誰に投票するか、正直まだ決めきれていない。
でも、投票に行かないという選択肢はない。
技術者として、自分で考えて決断する訓練をしてきた。
だからこそ、今回もギリギリまで情報を見て、自分なりに「納得できる一票」を投じたいと思う。
SNSがどうあれ、候補者の話がつまらなくても、未来がどうなるかわからなくても、
“何も選ばない”よりは、ずっとマシだと信じている。