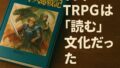技術者の心を揺さぶった「新プロジェクトX」再放送
先日、NHKの「新プロジェクトX ~挑戦者たち~」の再放送を見ました。
今回のテーマは、あのソニーの家庭用ゲーム機「プレイステーション」の開発秘話でした。
見終わったあと、私は深い感動と同時に、どこか懐かしい気持ちに包まれました。
若い頃に胸を躍らせながら発売日にプレステを手に入れたあの日の興奮と、ものづくりに夢中だった頃の情熱が、一気に蘇ってきたのです。
私は現在50代で、製品ハードの回路設計に携わってきたエンジニアです。
技術一筋でここまでやってきて、そろそろ定年も意識するようになりました。
そんなタイミングでこの番組を見たことは、きっと偶然ではなかったのだと思います。
発売日、あの頃の自分を思い出して
プレイステーションが発売された当時、私は大学生でした。
ゲームが大好きで、アルバイト代を貯めて発売日に購入したことを今でもはっきり覚えています。
あの「1・2・3!」のCMが流れるたびに、胸が高鳴りし、あのキャッチーなリズムに、「何か新しい時代が来る」と直感したものです。
ただ、当時はセガサターンも同じ時期に登場しており、正直どちらを買うか迷いました。
セガのアーケードゲームは本当に魅力的で、サターンにも心惹かれていました。
それでも最終的にプレイステーションを選んだのは、ソニーが掲げていた「どのソフトメーカーにも門戸を開く」というコンセプトに共感したからです。
セガが自社タイトル中心だったのに対し、ソニーはオープンな姿勢でソフトメーカーを受け入れていました。
その柔軟さが、これからの時代に合っている気がしたのです。
当時は「ファイナルファンタジーが次はスーパーファミコンではなく、プレステで出るらしい」という噂が広まっており、それも後押しになりましたし、さらにナムコがリッジレーサーや鉄拳といった3Dゲームをプレステで開発していると聞いて、心は完全にプレステに傾きました。
実際に手にして遊んでみると、ポリゴンがリアルタイムで滑らかに動く光景に驚き、まるで未来を体験しているような気分でした。
当時はまだ学生で、電子回路の勉強を始めたばかりのそんな中で、プレイステーションの中身や構造が気になって仕方がなかったのを覚えています。
技術が遊びと直結していたあの時代、ゲーム機は私にとって“技術の象徴”でもありました。
技術者として心に響いた、開発者たちの挑戦
番組では、ソニーと任天堂が共同でゲーム機を開発していた“幻の試作機”の話から始まりました。
両社の提携が破綻し、ソニーが単独でゲーム機を開発することになったというくだりは有名ですが、実際に現場のエンジニアたちがどんな思いで動いていたのかを聞くと、胸が熱くなりました。
リアルタイム3Dを家庭用ゲーム機で実現するというのは、当時の技術水準では“無謀”ともいえる挑戦だったそうです。
それでも彼らは諦めず、社内の批判や開発中止の危機を乗り越えていきました。
特に印象に残ったのは、東芝の半導体技術者との出会いによって技術的な壁を突破したというエピソードでした。
異なる企業の技術者同士が、「面白いものを作りたい」という共通の情熱でつながった瞬間でした。
この話を聞いて、私は思わず自分の仕事を重ねてしまいました。
私も長年、製品ハードの回路設計を担当してきましたが、開発というものは常にトラブルと紙一重です。
ノイズ、発熱、信号の遅延、コスト制約……など、どんなにシミュレーションを重ねても、現場でしか見えない問題が次々に出てきます。
そんな時に最後の一押しをするのは、結局「絶対に動かしてやる」という技術者の意地なんですよね。
「プロジェクトX」に登場した開発者たちの言葉には、そうした現場のリアルな熱がこもっていました。
彼らもまた、誰かに褒められるためではなく、純粋に“面白いものを作りたい”という思いで突き進んでいたのです。
その姿を見て、自分も原点を思い出しました。
定年を意識する今、改めて感じたこと
50代も後半に差し掛かり、私もそろそろ定年を意識してしてきます。
若い頃のように徹夜で回路を引くような体力はありませんし、今では若手を育てる立場にもなりました。
毎日がルーチン化していく中で、いつの間にか「挑戦」よりも「安定」を優先するようになっていた気がします。
そんな中で見た今回の番組は、まるで心に火をつけられたようでした。
ソニーの開発チームが、常識を超えて新しいものを作り出す姿を見て、「自分もかつてはあんな気持ちで仕事をしていた」と思い出しました。
効率よりも面白さを、手間よりも探求を優先していたあの頃。あの感覚を、もう一度取り戻してみたいと思ったのです。
定年後は、自由な時間を使って自分のための設計をしたいと考えています。
仕事ではなく、趣味の延長としての電子工作。小さなマイコンボードやLED回路を作って、手を動かしながら実験する。
結果が出たら、それを眺めてにやりと笑う。
そんな時間を、これからの“第二のエンジニア人生”として楽しみたいのです。
プレイステーションが教えてくれた“開かれた設計思想”
プレイステーションが成功した要因の一つは、ハードを「開かれたプラットフォーム」にしたことだと思います。
セガサターンが自社の強みを押し出す戦略だったのに対し、ソニーはソフトメーカーに門戸を開き、自由な発想を受け入れる環境を整えました。
これは私の仕事にも通じる話です。
回路設計も同じで、閉じた設計をすると拡張性がなくなり、結果的に製品の寿命を縮めてしまう。
逆に、他の技術者が扱いやすい構造や拡張性を持たせると、プロジェクトが生き延び、後の世代に受け継がれるというオープンであることの大切さを、プレステの設計思想から改めて学びました。
また、「ゲーム機」という言葉で片付けられがちな製品ですが、その中には多くの技術者の汗と努力が詰まっています。
数百本の配線、数千の部品、緻密な信号制御。それを人の笑顔に変えるのが、ものづくりの醍醐味です。
私もこの業界に長く身を置いてきましたが、どんな小さな製品にも、誰かの「夢中」が詰まっている。
そんな当たり前のことを、番組を通じて思い出しました。
これからの自由なものづくりへ
「新プロジェクトX」で描かれたエピソードは、単なる成功物語ではありませんでした。
リスクを恐れず、理想を信じ、失敗を繰り返してでも進み続けた技術者たちの姿がそこにありました。
それは、今の自分にも必要なメッセージに感じました。
これから定年を迎え、会社という枠から離れても、私はずっと“設計者”であり続けたいと思います。
誰に頼まれなくても、自分の手で何かを作り出すしたい。
失敗しても、時間を気にせず、自分のペースで試行錯誤を楽しみ、動かして喜びを得たい、そんな生き方をしていきたいのです。
あの日、大学生だった私は、プレイステーションを手にしてワクワクしていました。
今の私は、回路図を前にして同じようにワクワクしていますし、最近はC言語も少し覚え、AIも使用しています。
技術者としての人生は、まだ終わりではありません。次の挑戦は、きっとこれから始まるのだと思います。