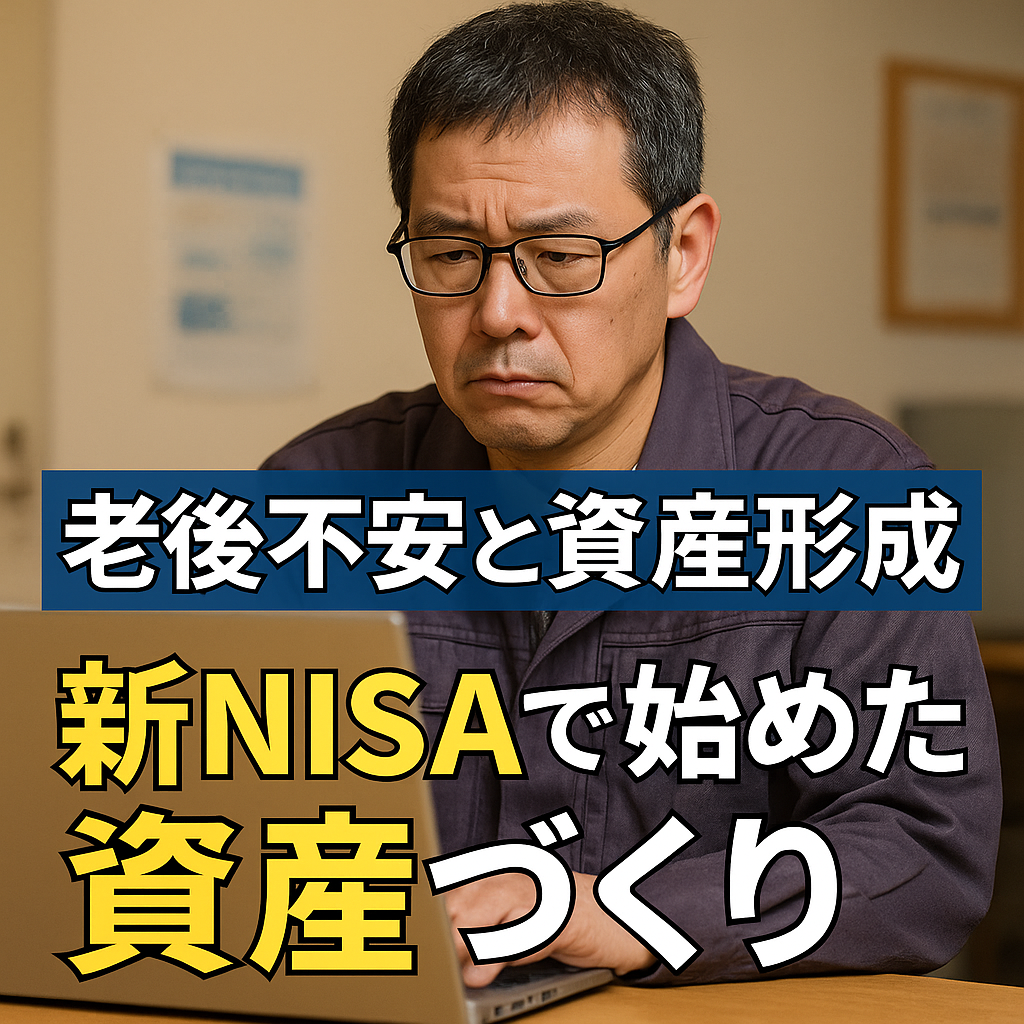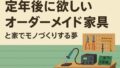SmartNewsに並ぶ「老後不安」系ニュースたち
最近、通勤中やちょっとした隙間時間に何気なくSmartNewsを開いていると、どうにも同じようなテーマの記事ばかりが目につきます。
「40代から50代で貯蓄額はどのくらい変わる?」
「45歳サラリーマン、年収○○○万円を捨てて手に入れた暮らし」
「貯蓄○○○万円で老後を安心して過ごせると考えていた夫婦の悲劇」
とにかく「老後」「貯蓄」「退職」「後悔」といったキーワードが、目に入ってくるたびに胸がざわつく今日この頃です。
特に、自分がちょうどその年齢層にさしかかっているとあっては、気にならないわけがありません。
正直、こういった記事の多くは煽り気味のタイトルでクリックを誘っているのもわかっているんですが、それでもついつい読んでしまうのは、それだけ“将来への不安”が無意識のうちに大きくなっているからなんだと思います。
「老後2000万円問題」でようやく火がついた資産形成
そういえば、少し前に「老後2000万円問題」がわだいになったの覚えているでしょうか?
当時は「そこまで深刻に受け止めなくても……」という空気もありましたが、個人的にはあれが資産形成を考えるきっかけになりました。
「年金だけじゃ足りない」と言われても、じゃあ何をすれば良いのか?
投資か、保険か、副業か?
色々な情報が飛び交う中で、まず自分にできそうなことは何かと考えたとき、選んだのが株式投資でした。
とはいえ、最初はおっかなびっくりの世界でした。
旧NISA制度もあったものの、正直株なんかよくわからりませんでしたが、証券会社に口座を開設して余剰金を振り込み安い米国株を購入して放置状態にしていました。
新NISAスタートで投資意欲に火がついた
そんな中、新NISA制度が2024年からスタートしました。
これが大きな転機となりました。
制度の刷新によって、非課税保有限度額が拡充され、より使いやすく、かつ長期での資産形成に向いている仕組みに変わったことで、「今度こそちゃんとやってみよう」と思えるようになりました。
成長投資枠と積立投資枠の組み合わせで、年間最大360万円の非課税投資が可能で、しかも生涯投資枠として1800万円というのも現実味があり、「ちょっと頑張れば手が届きそう」という感覚が背中を押してくれました。
毎月の積立額はまだ大きくありませんが、少しずつ、自分の生活スタイルに合わせて無理なく続けられる金額で運用を始めています。
定年退職を自分で決めるために
資産形成のモチベーションにはいろいろありますが、個人的に大きいのは「定年退職を自分の意志で決めたい」という思いです。
世の中には、定年延長制度や再雇用といった選択肢もありますが、それは“選ばされる”のではなく、“選べる”ようでありたい。
そのためには、会社の給与に依存しなくても一定の生活が成り立つだけの備えが必要になります。
もちろん、年金や退職金、貯金も含めて全体的な資金計画が重要なのは言うまでもありません。
ただ、その中でも投資によって得られる「増やす力」は、これからの10年で特に意識すべきポイントだと思っています。
情報過多の時代に「何を信じるか」
ただ、情報収集していると感じるのは、情報の多さが不安を煽ることもあるということです。
SmartNewsに限らず、X(旧Twitter)、YouTube、Facebookなど、SNSやメディアには老後やお金に関する情報が山のように流れてきます。
中には極端な成功例や不安を煽るだけの記事も多く、何を信じて行動すべきか分からなくなることもしばしばあります。
しかも、最近はAIが自動で“興味ありそうなニュース”をどんどん表示してくるため、こちらが一度「老後」や「貯金」と検索しようものなら、そればかりが並ぶようになります。
あれもこれも気になってしまって、むしろ行動に移せなくなってしまう、なんて本末転倒なこともあります。
新NISAの運用実績や投資額も、今後記事にしていきたい
今はまだ、新NISAを始めて間もない段階です。
積み立てている金額も小さいですし、銘柄もまだ様子見で選んでいる状態です。
とはいえ、少しずつ積み重ねた結果や、なぜその銘柄を選んだのかといった判断の記録は、今後ブログの形で残していけたらと思っています。
同じように資産形成を始めたばかりの方にとって、何か参考になることがあればうれしいですし、自分自身にとっても振り返るきっかけになると思います。
「備えながら、楽しむ」バランスを大切に
最後に思うのは、老後への不安を解消するために、今の生活を犠牲にしすぎても本末転倒だということです。
備えは大切ですが、同時に今の暮らしもちゃんと楽しむことができなければ意味がない。
そんなバランス感覚を忘れずにいたいとは思うので、日々のニュースに流されすぎず、自分のペースで、無理なく資産形成を進めていく──それが理想です。
新NISAはそのための有効なツールだと思っています。
制度を上手く活用しながら、これからも地道に積み上げていこうと思います。