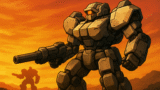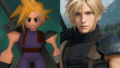あのロボットに再び命を吹き込む日が来るとは『カルネージハート』と思考で戦う楽しさ
製品ハード開発のエンジニアとして、もう30年近くこの業界に携わっている定年まじかな人間です。
仕事に追われる毎日の中、最近は「定年まであと何年」と数えることが増えました。
正直なところ、早く自由気ままな生活を送りたい。
それが今の密かな願いです。
そんなある日、ふと見たYouTubeの動画で昔のことを思い出しました。
まだ20代だったころ、夜な夜な夢中になってプレイしていた1本のゲームがあったんです。
その名は『カルネージハート』!
名前を聞いて懐かしいと感じたあなた、きっと同世代ですね。
あの頃の私は「自分で考えるロボットを作って戦わせる」という未知の遊びに夢中になっていました。
【カルネージハートの歴史と進化を知りたい方はこちら】
「動かす」のではなく「考えさせる」ロボットゲーム
1995年、PlayStationで発売された『カルネージハート』というゲームをご存じでしょうか?
一見するとロボットを操作して戦うアクションゲームのように見えますが、実際にプレイヤーが行うのは操縦ではなく“思考の設計”です。
ロボットに搭載するAIをフローチャート形式でプログラムしていくというものです。
「敵を感知したら回避行動へ移れ」「攻撃を受けたら武器を切り替える」「オーバーヒートしないように冷却を挟む」など、条件と動作を細かく設計していきます。
初めて雑誌で紹介記事を見たとき、「なんだこのゲームは?」と驚いたのを今でも覚えています。
実際にプレイしてみると想像以上の奥深さがあり、時間を忘れてAI設計に没頭しました。
思い通りに動かないロボットを見ながら「ここで回避に入らないのは条件が抜けてるのか」「敵を認識するタイミングを変えたらどうなるか」と試行錯誤を重ねる日々が続きました。
意図通りにロボットが動き、敵を撃破した瞬間は思わずガッツポーズをしてしまうほどの達成感でした。
あの「自分の作った思考が勝利する」という感覚は、他のどんなゲームでも味わえないものでした。
自分だけのロボットが“戦う”ことの奥深さ
カルネージハートの魅力は、単にロボットをデザインしたり操作したりすることではありません。
それ以上に「思考そのものをデザインする」という点にありました。
敵との戦いは、単なるアクションではなく論理と感性のぶつかり合いで、限られた命令数やパーツの中で、どうすれば勝てるかを考え抜くという作業は明確な正解が存在せず、トライアンドエラーの連続でした。
このゲームを通して「失敗は改善のチャンスである」という思考を自然と学びました。
負けるたびにAIロジックを修正し、原因を分析して再挑戦する。
今思えば、現在のエンジニアリングにも通じる“開発サイクル”を、当時は遊びの中で経験していたのだと思います。
当時は友人と互いのロボットを持ち寄って戦わせることもよくありました。
相手が自分の戦略を上回るロジックを組み上げてきたときの悔しさ、そしてそれを超えるために考え抜くという繰り返しが本当に楽しく、今でも強く記憶に残っています。
【カルネージハートにハマった思い出記事】
現代に蘇る“令和版カルネージハート”『Gladiabots』
そんな懐かしい思い出を胸に、最近「カルネージハートのようなゲームはもうないのか」と探してみたら、見つけたのが『Gladiabots(グラディアボッツ)』という作品です。
このゲームもプレイヤーがロボットのAIを設計し、そのロジックに従って戦わせます。
まさに令和版カルネージハートと呼べるタイトルだと思い増しました。
『Gladiabots』はSteamのほか、AndroidやiOSでもプレイ可能です。
グラフィックはシンプルですが、AI構築の自由度が高く、世界中のプレイヤーとAIバトルを競える点が魅力です。
ネット上では「プログラム設計が楽しい」「AIが思った通りに動いたときの快感が最高」と高評価が多く、カルネージハート経験者からも支持を集めているようです。
まだ実際にプレイはしていませんが、動画を見ているだけでもワクワクが止まりません。
思い通りに動かないロボットを調整しながら、少しずつ理想の動きを作り上げる。
そんな“思考で戦う面白さ”をもう一度味わえる予感があります。
カルネージハート好きにおすすめの思考型ロボットゲーム
カルネージハートやGladiabots以外にも、思考型・ロジック構築系のゲームはいくつか存在するようで、これらは「考えること」そのものが楽しいと感じる人にぴったりの作品となっていると好評です。
- 『Human Resource Machine』
プログラミングの基礎をゲーム感覚で学べる名作。命令を並べてタスクを自動化する発想はカルネージハートに通じます。 - 『Factorio』
自動化ラインを構築して効率を突き詰める“思考ゲーム”。論理的な最適化の快感があります。 - 『RoboCraft』
ブロックを組み合わせてロボットを作り、オンラインで戦うクラフトアクション。設計思想が近く、カスタマイズ性も魅力です。 - 『Mindustry』
資源管理と防衛を組み合わせた自動化タワーディフェンス。命令パターンを構築していく楽しさがあります。
これらのゲームを通じて、現代に進化した「思考型ロボット戦略」を体験できるようです。
あの頃のワクワクを、もう一度思い出してみませんか?
仕事もベテランの域に入り、若い頃のような高揚感を感じる機会は減ってしまいました。
それでもカルネージハートを思い出すと、不思議と心が熱くなります。
考えて、組んで、失敗して、また挑戦するというそのサイクルこそが、ものづくりの原点だったのかもしれないと最近考えます。
自分のロボットを育てていたあの時間は、ただの遊びではなく、今の自分を作った大切な経験でした。
もしこの記事を読んで「懐かしい」と感じたなら、ぜひ一度『カルネージハート』や『Gladiabots』をのぞいてみてください。
きっとあの頃の熱量を、もう一度取り戻せるはずです。
定年後にやりたいことリストに「ロボット再入門」を追加
この歳になると「いつかやりたいこと」が具体的に見えてきます。
私にとってそのひとつが「再び自分のロボットを作って動かす」ことです。
趣味でも、ゲームでも構いません。
自分の手で“考えるマシン”を設計し、動かすあの感覚をもう一度味わいたい。
定年までの数年間で、『Gladiabots』をはじめとした思考型ロボットゲームを再び楽しみ尽くしたいと思っています。
いつか、自分の作ったAIロボットがまた誰かのロボットと戦う日が来たら、そのときは若い頃の自分と再会できるような気がします。
「思考するゲーム」は時代を超える
『カルネージハート』が発売された1995年当時、AIや自動化はまだ遠い未来の技術でした。
しかし今、AIが身近になった時代にあらためて感じるのは、「考えること」そのものの面白さは決して色あせないということです。
AIが進化した今だからこそ、自分の思考で戦うロボットゲームはより深く感じられる。
ゲームを通して論理を設計し、創造し、改善する体験は、仕事にも人生にも通じる普遍的な喜びです。
あの頃のように、自分の作った“思考”が戦う姿を、もう一度見てみたいと考える今日この頃です。
カルネージハートのように、ロジックを組み、改善を繰り返すゲームは他にも存在します。
「操作より思考が楽しい」と感じる理系エンジニア向けに、特にハマりやすいゲームを3本厳選してまとめました。