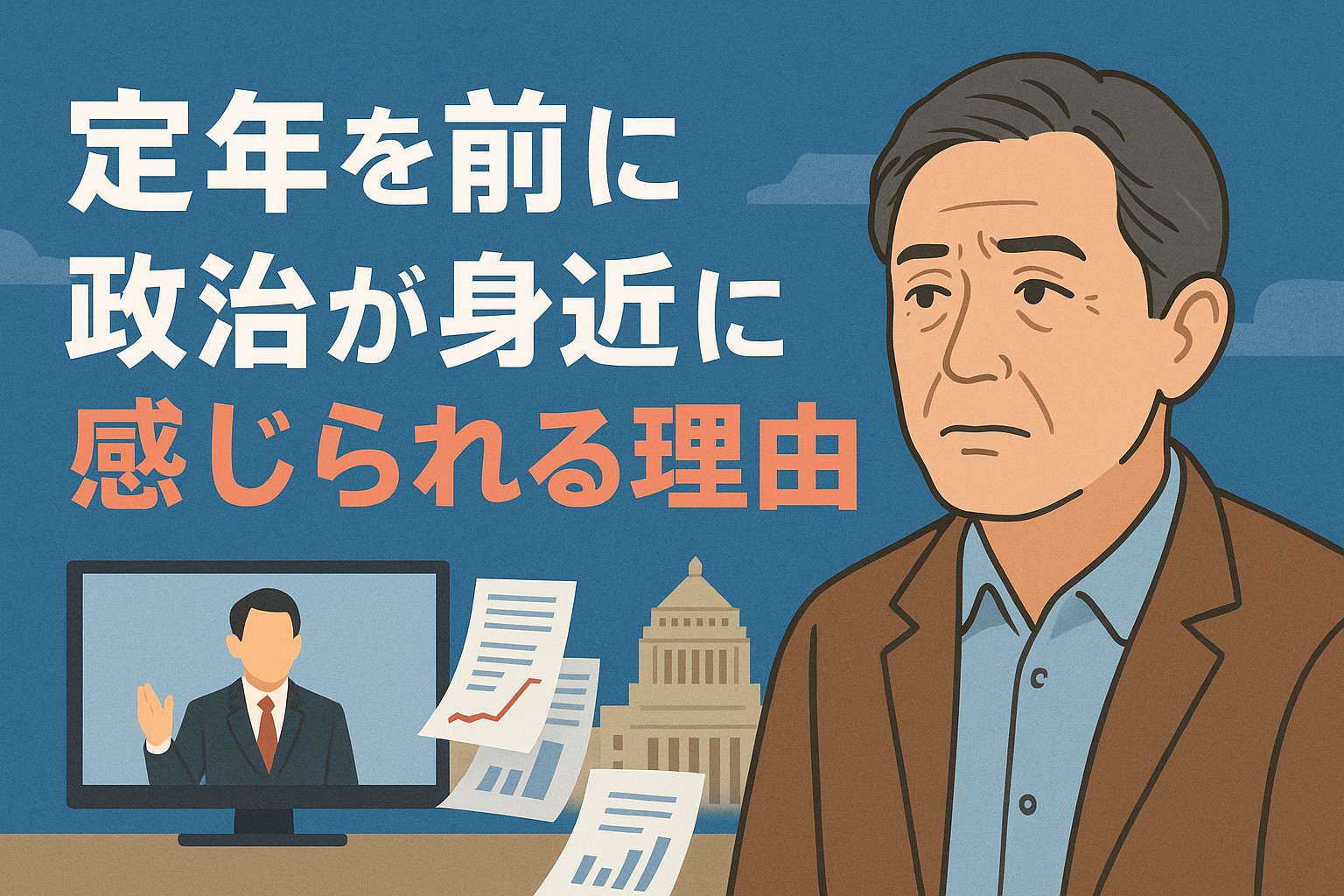50代前くらいから政治が身近になってきた理由
2025年の自民党総裁選が迫り、テレビや新聞、ネットニュースでも連日取り上げられています。
私自身、若い頃は政治にさほど関心を持っていませんでした。
仕事である製品ハードの開発に追われ、目の前の課題をどう解決するかが日常のすべてだったからかもしれません。
しかし、50代前くらいになってからでしょうか?
子供が大きくなり老後を考えだしたときに、将来の暮らしを考えるようになると、政治がぐっと身近に感じられるようになりました。
年金や医療費、介護、さらには物価や税金の問題など、どれも私の生活に直結するテーマです。
その大きな鍵を握るのが、自民党の総裁選だと思います。
なぜなら、自民党は長年日本の政権を担ってきており、総裁に選ばれた人物がそのまま総理大臣になる可能性が非常に高いからです。
つまり、自民党の総裁選は「日本の次のリーダーを選ぶ選挙」と言っても過言ではありません。
自民党総裁選の仕組みを理解する
ここで、総裁選の仕組みを整理しておきましょう。
立候補の条件
自民党総裁選に立候補するには、自民党所属の国会議員であり、さらに20人の国会議員から推薦を受ける必要があります。
人気があっても推薦人を集められなければ出馬できないため、党内での人脈や信頼が大きな意味を持ちます。
投票の流れ
投票は大きく二段階です。
- 第1ラウンド
自民党の国会議員(約300人)がそれぞれ1票を持ちます。さらに、全国の党員・党友による投票結果が同数(約300票)に換算され、合わせて約600票で競う形になります。過半数を獲得した候補がいれば、その場で総裁が決まります。 - 決選投票
過半数を獲得できなかった場合は、上位2名による決戦となります。このときは国会議員票(約300票)に加えて、47都道府県連の代表票が1票ずつ加わります。合計343票で争われるため、議員の意向がより強く反映される仕組みです。
こうして見ると、自民党総裁選は単なる人気投票ではなく、党員の声と議員同士の力学が入り混じった仕組みだと分かります。
過去の総裁選から見えること
歴史を振り返ると、総裁選はしばしば政権の方向を大きく変えるきっかけになってきました。
たとえば2001年の小泉純一郎氏の登場は、自民党に新風を吹き込み、国民的人気によって政治への関心を高めました。
逆に、党員の人気が高くても議員票で敗れるケースもあり、最終的には「党内の合意形成力」が問われるのです。
2025年の立候補者たち
※以下の候補者紹介は、私が報道などを参考にしながら個人の意見を交えて整理したものです。
必ずしも客観的な評価ではなく、一人の生活者としての視点でまとめています。
小林鷹之
比較的若手で、経済や科学技術政策に強みがあります。AIや半導体といった分野に積極的で、未来志向の政策を打ち出しています。若い世代や新しい産業を重視する層にとっては注目の存在です。
小泉進次郎
若手時代から国民的な人気を誇り、演説力や発信力に定評があります。環境問題や子育て支援などで積極的に発言してきましたが、政策の具体性や実行力には疑問の声もあります。議員票をどこまで伸ばせるかが焦点です。
高市早苗
保守的なスタンスで、特に外交・安全保障政策に強いこだわりがあります。台湾や防衛費増額など、国際情勢が不安定な中で注目される候補です。一方で、社会保障や経済政策にどの程度の具体策があるのかも問われています。
林芳正
外務大臣経験があり、国際的なネットワークや交渉力に強みを持ちます。議員間での調整力もあり、「安定感のあるリーダー」として期待されています。外交重視の姿勢は、今後の国際社会での日本の立場を考えると大きなポイントです。
茂木敏充
豊富な経験を持つベテランで、党内での調整力に長けています。官僚とのパイプも強く、安定路線を求める層に支持されています。ただし新鮮味に欠けるという声もあり、国民からの支持をどこまで広げられるかが課題です。
暮らしや老後に直結するテーマ
私自身が最も関心を持っているのは、やはり経済と社会保障でしょうか?
物価が高止まりし、給与の伸びが鈍い中、老後の生活資金には不安がつきまといます。
もし増税が進めば定年後の暮らしはさらに厳しくなると思っていますが、国の財政を放置することもできません。
個人の家計と国の借金、この難しいバランスに次の総裁がどう向き合うかが重要です。
また、技術者として働いてきた立場からは、科学技術政策も気になります。
AIや半導体などで世界が激しく競争している中、日本が出遅れれば産業基盤が揺らぎます。
小林鷹之氏のように技術に力を入れる候補がいるのは心強いです。
研究開発や産業支援が進めば、私たちの日常にも確実にプラスの影響があるはずです。
政治は遠いようで実は身近
政治家の演説を聞くと「現場の生活を本当に分かっているのだろうか」と感じることがあります。
立派なスローガンを掲げても、実際に上がり続ける電気代や食費にどう対応するのかが気になるのです。
私たちが本当に知りたいのは「年金は安心できるのか」「医療や介護は十分に支えてもらえるのか」「定年後も普通に暮らしていけるのか」といった具体的な点です。
そこに候補者がどう答えるのかを注目して見ていきたいと思います。
定年後を安心して迎えるために
私はあと数年で定年を迎えます。
自由に過ごせる時間を楽しみにしている一方で、社会が不安定では心から安心できません。
だからこそ総裁選を「遠い世界の権力争い」ではなく、自分の暮らしに直結する出来事として受け止めています。
政治は難しいと感じがちですが、仕組みを少し知り、候補者の特徴を整理するだけで、自分の生活と結びつけて考えられるようになります。
派手なパフォーマンスよりも、地に足のついた政策を進めるリーダーを選んでほしい。そう願いながら、今回の総裁選を見守りたいと思います。